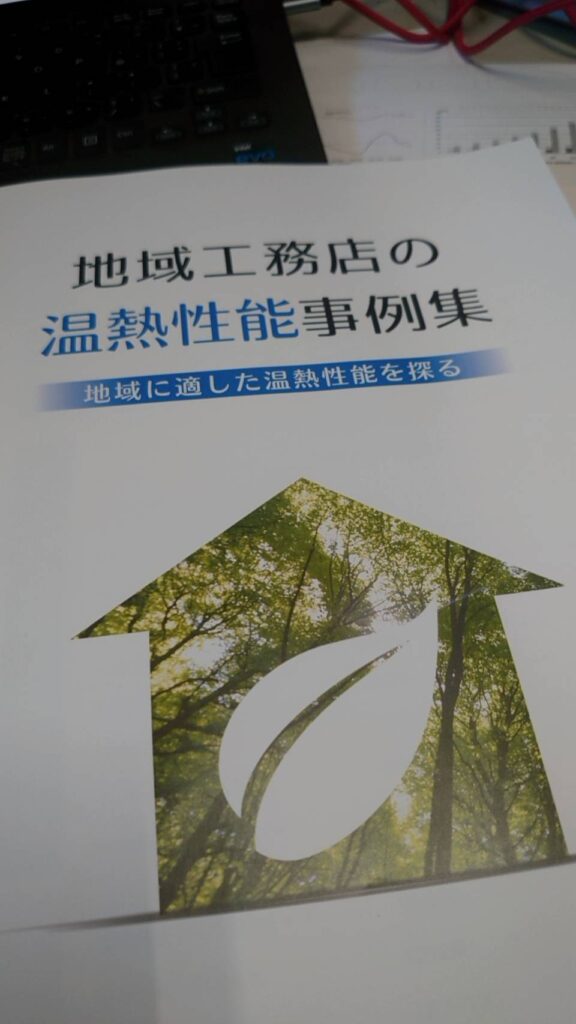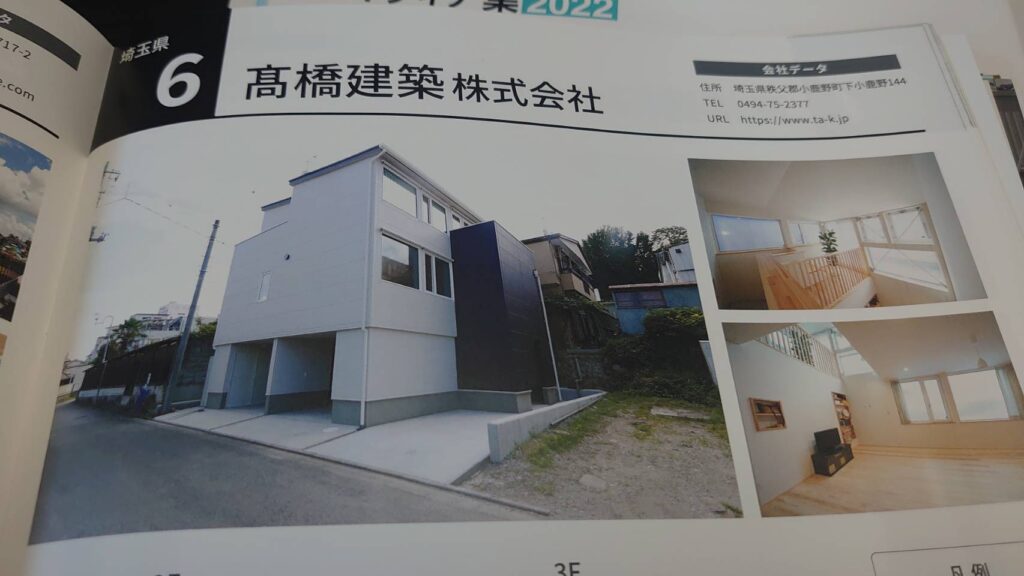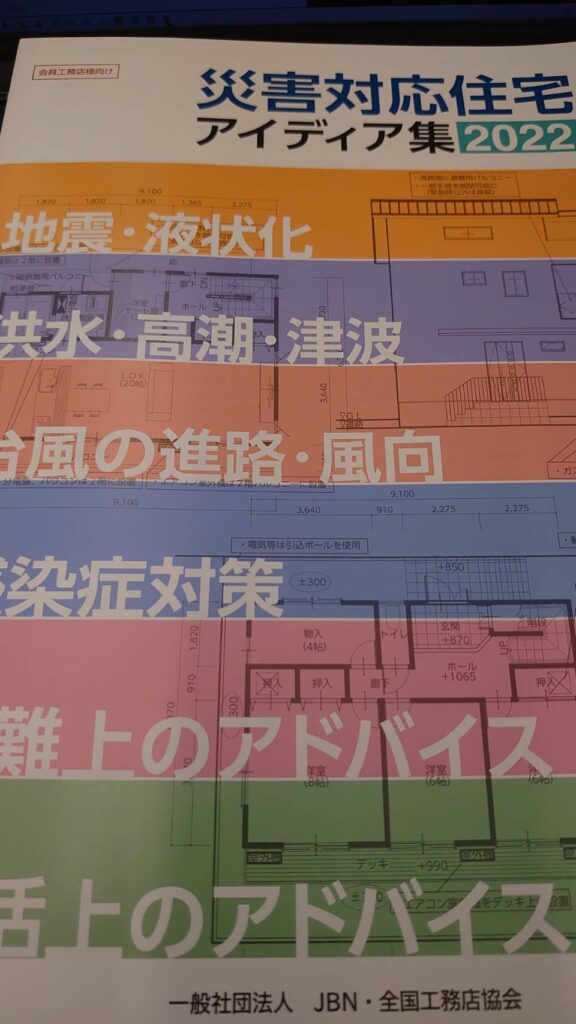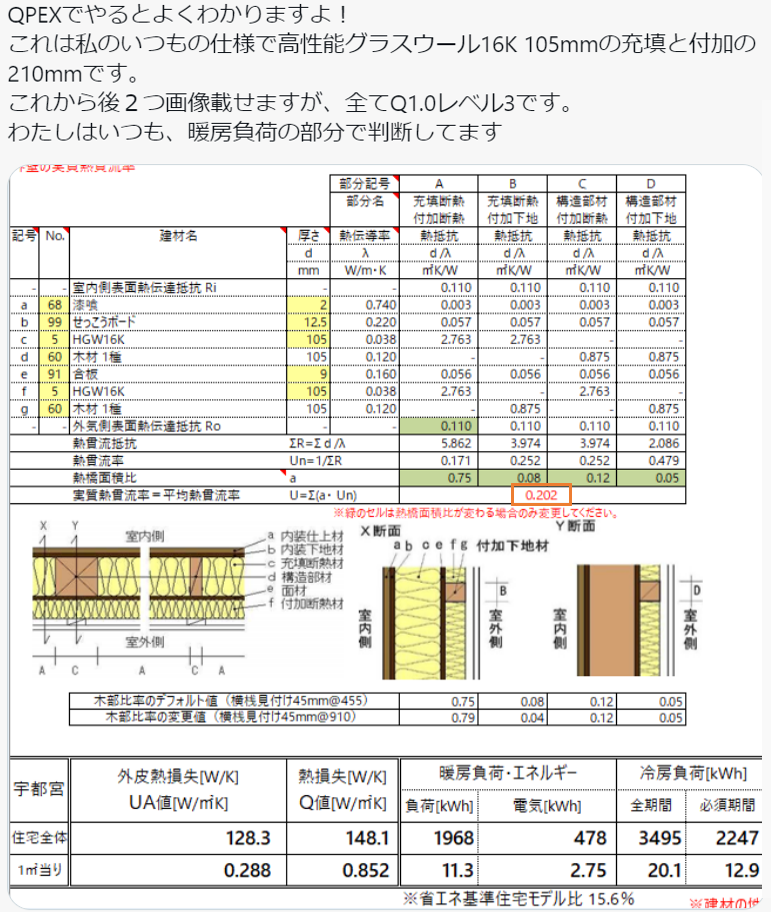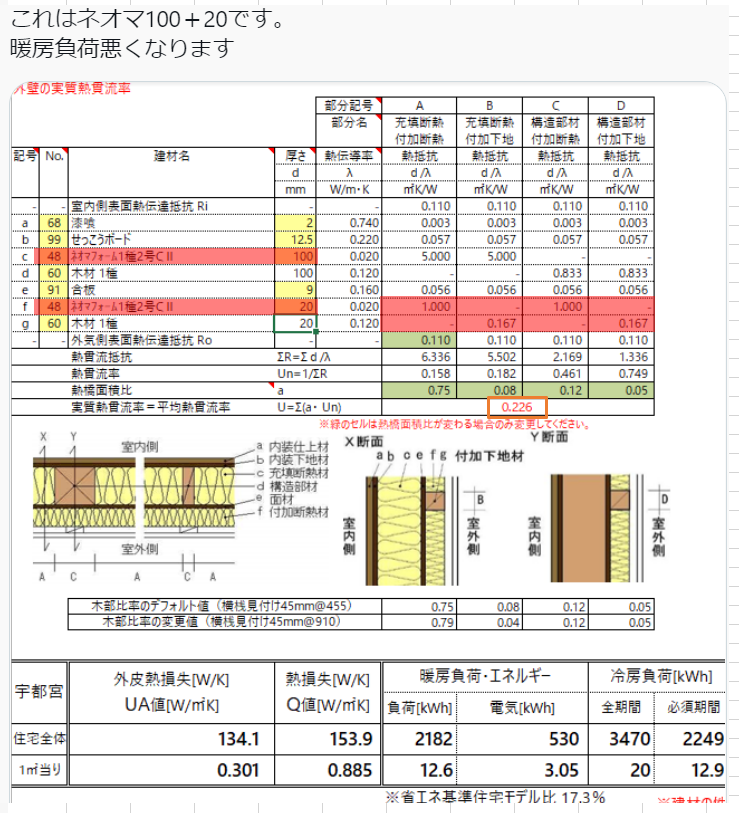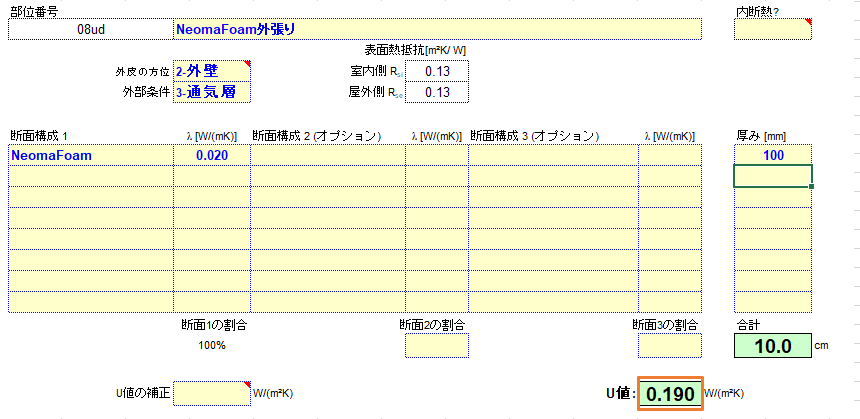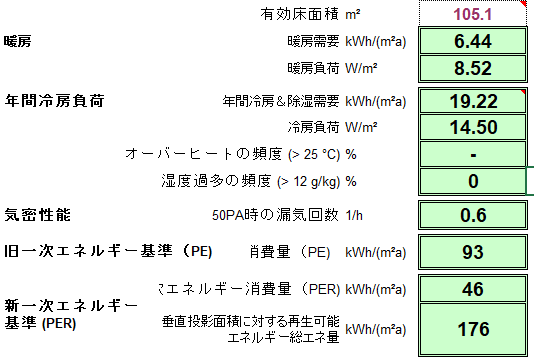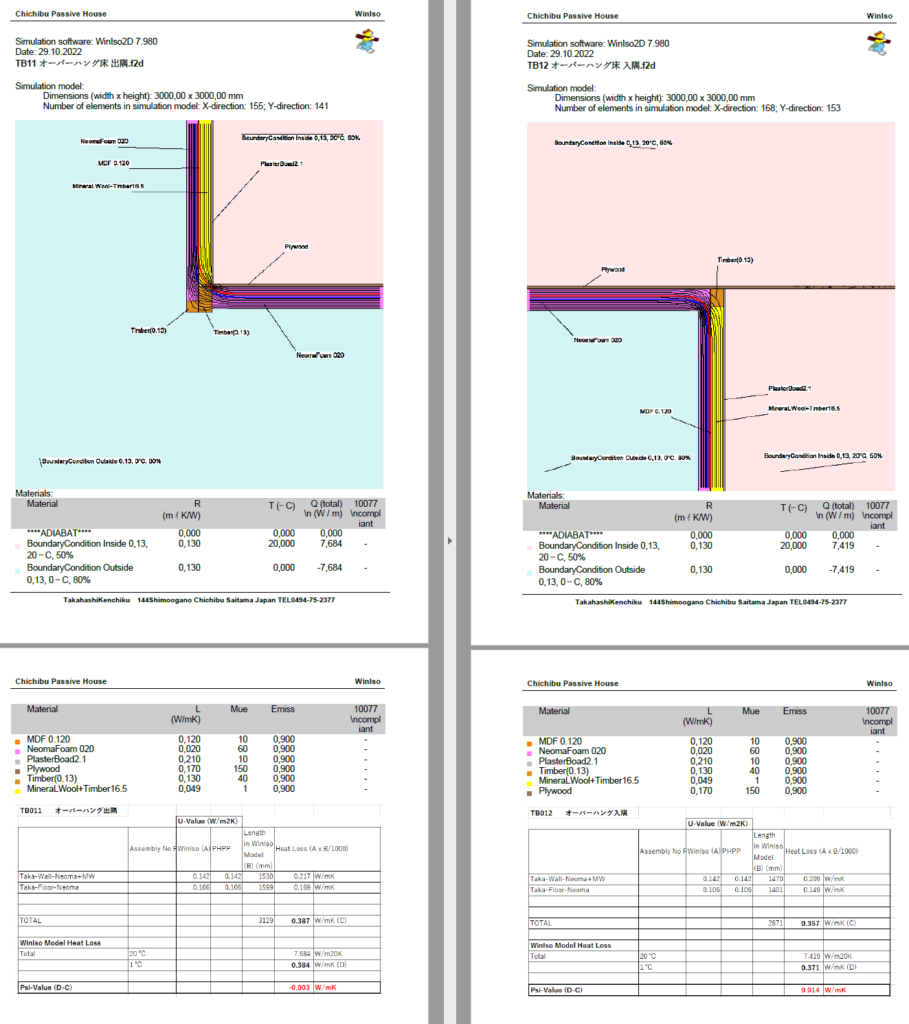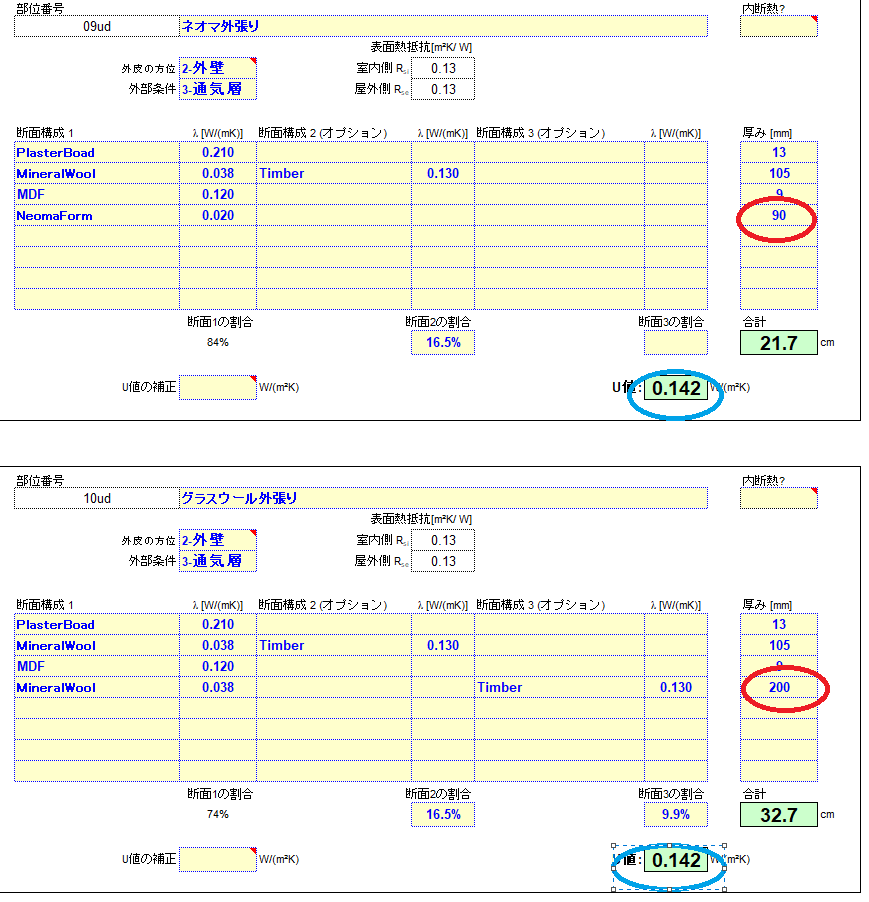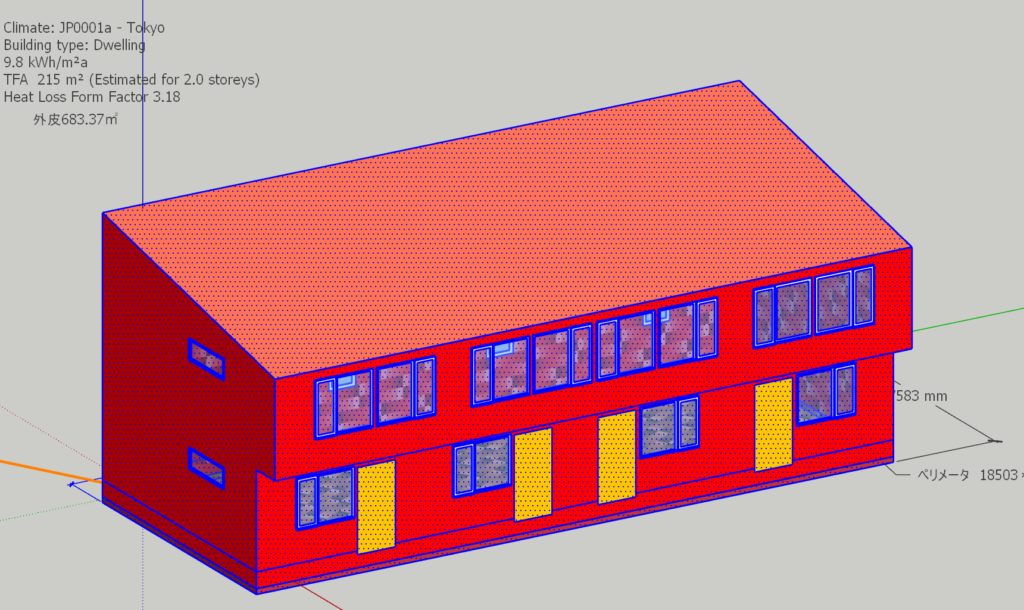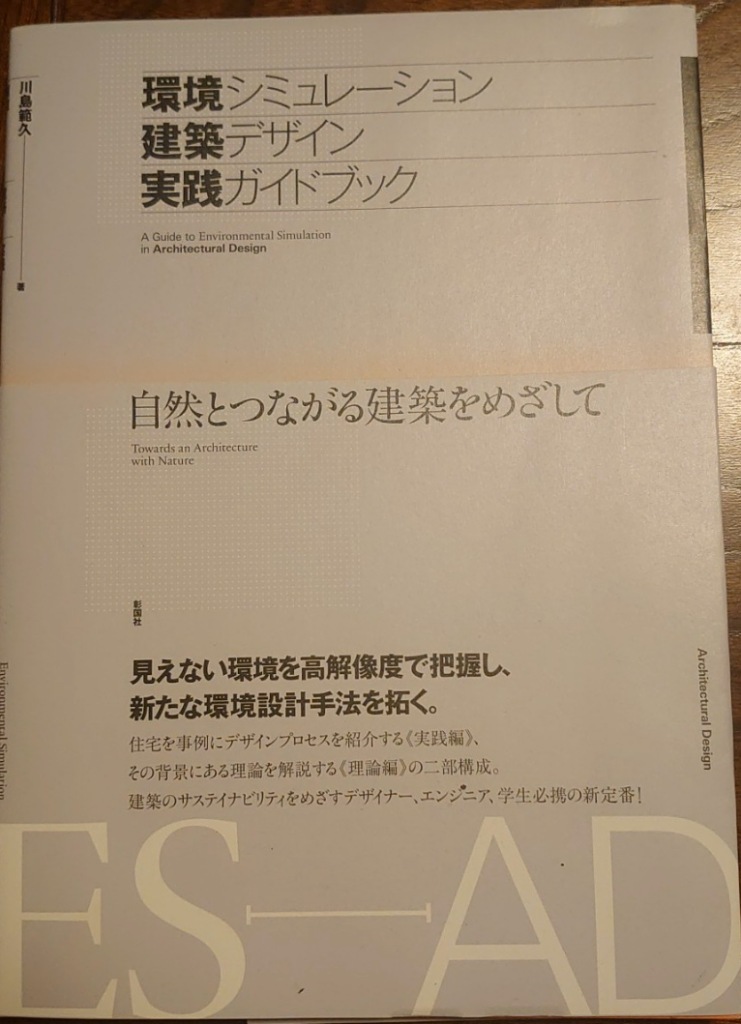youtubeで断熱性能の違いについての動画が流れていたので見ました。
最近のyoutubeは、以前よりもきちんとした情報を流している人も出てきていますので、一般の方がどのような情報をほしがっているか?
一般の人より知識のあるyoutuberがどのように考えているのか?どのくらいの知識があるのか?どんな説明をしているのかを知るために割と見ています
本当にいい加減な内容ばかりの人のものは見ませんけど、割とまともなやつを見ています。
youtuberの力
youtuberのちからは大きいです。一般の方はかなり影響されています。
建築の情報をわかりやすく伝えると言うことでは、とてもありがたいと思っています。
間違いもたくさんありますが、一般の人が知るべきレベルの情報の認識として、まあそれくらいの間違いは良いか。と思いますので、全く間違えてなければ、youtuberの個人の意見として、まあ良いか。と思っています。
ですが、最近のお客様は、きちんと勉強されている人が多いので、この間違った情報で勉強してしまうと残念だな。と思います。せっかく勉強したのにこのyoutubeのせいで間違えた判断をしてしまうことになりかねません。
その間違えた情報で判断してしまうとすごく孫をしてしまう場合もありますよね。
YOUTUBERも勉強
youtuberに悪気があるわけではないですし、youtuberの方も一般の方に正確な情報を伝えようと努力してくれています。きちんとしたyoutuberのかたは本当に努力されています。
youtuberのかたと 様々セミナーなどでお会いする機会もあります。この人が勉強していて正しい情報が多い。というのは名指しで言うことは控えますが、きちんと勉強して情報発信するのありがたいですね。
最近では、パッシブハウスジャパンで行っている「省エネ診断士」の講習会でもyoutuberの方が参加されてくださってます。
きちんとした情報を獲得し、正確な情報で一般の方に伝えていただけると本当にありがたいですね。
応援しています。私たちもできるだけわかりやすく正確に学んでいただけるように頑張っています。
youtuberのかたがきちんと勉強し、正確な情報できちんと発信し、お客様がきちんとした情報で勉強してくださっていると、話が早くて私たちもありがたいです。
洗脳と同じ
かなりフォロアーが多い方でも、いい加減な人もいるので注意が必要です。皆さんせっかくの勉強が無駄になります。そういうyoutuberは話術が旨いので間違えた知識をすり込まれてしまいます。
宗教団体の洗脳と同じですね。
私たちが話を聞いていても話に引き込まれていきます。
間違っている情報や、自分勝手な情報がとても多いです。
その人の思い込みで本当にそれを信じていて、それを皆に伝えることが大切と思い込んでいるので本当に困りますね。
話術で、その人の言うことが正しく聞こえ信じ込んでしまうでしょう。
そしてその人の言うことがすべて正しく聞こえてします。
洗脳ですね。
情報をフォローしないと
あまりにも根本的に間違えている情報は、私たちが適切にフォローしないといけないですね。
その人のyoutubeでコメント入れるのはその人の自尊心を傷つけてしまったりするので、しない方が良いですね。
発言力の大きい、youtuberを敵に回すと後々大変そうです。
メルアドでも知っていれば影で教えてあげることも出来るとは思いますが、それでも怖いですね。
youtuberの人はちょっと怖いです。
まあ、当社のホームページにたどり着いた人が正しい知識を得てくれれば良いので、このブログの中で訂正させていただいていこうと思います。
youtuberの人は跡でどこかで気がつけば良いということにしましょう。